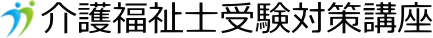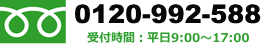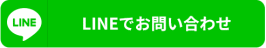米子市の皆様、介護福祉士講座の5つの特長です
米子はこんな町です
米子市(よなごし)は、鳥取県の西部の市で島根県と接する。山陰地方の中央部に位置する都市。 古くから商業都市として発展し、『山陰の大阪』とも呼ばれる。 JR境線・伯備線の分岐点として、国鉄時代には米子鉄道管理局が置かれ、国道9・180・181号が通り、米子空港をもつ山陰の交通の要地となっている。 鳥取大学医学部や山陰放送(テレビ・ラジオ併設局)などがあり、山陰の拠点都市の1つとなっている。なお、山陰両県を統括する機関は米子市か松江市に置くケースが多い。 本市を中心に山陰最大の人口を擁する米子都市圏が形成されている。また、隣接する松江都市圏・出雲都市圏とともに、雲伯地方に中海・宍道湖経済圏が形成されていると見なされる。 山陰最大の温泉地である皆生温泉は、日本におけるトライアスロン発祥の地としても有名[1]。 市域はほぼ平坦で、南部は大山の裾野として丘陵地になっている。日野川が米子平野を流れており、北西部は弓ヶ浜半島となっている。 弓ヶ浜半島からは大山がみえる。 日野川の水を取水として、米子市から境港市にかけて用水路「米川」が流れている。 戦国末期になって伯耆西部は出雲の東部とともに吉川広家が治めることになった。 1601年、伯耆国18万石の領主として中村一忠が封せられ、1602年ごろ、米子城は完成したといわれている。藩主中村一忠が11歳と幼少のため執政家老横田村詮が新たに米子藩城下町を建設し藩政を治めた。1609年藩主中村一忠が急死したため中村家は断絶した。 代わって1610年に加藤貞泰が入城した。“近江聖人”と呼ばれる中江藤樹が少年期を過ごしたが、加藤家の伊予大洲藩へ移封に伴い米子を去った。その後池田氏が治めていたが、1632年以後は池田氏家老荒尾氏が自分手政治 を行った。 1871年の廃藩置県で鳥取県となり、1872年に米子城の土地、建物は米子在駐の大四大隊の士族らに払い下げられた。 1889年町制を実施し、会見郡米子町となる。 2000年10月6日13時30分頃に発生した鳥取県西部地震は、マグニチュード7.3、最大震度6強(鳥取県境港市、日野町)を観測したが、犠牲者がゼロという奇跡的な地震であった。 2005年3月31日に(旧)米子市・淀江町が新設合併し、(新)米子市となる。当初は、境港市・日吉津村を含む4市町村での合併を予定していたが、境港市・日吉津村は住民投票の結果、合併反対派が多数となったため、強制合併はせず、結局実現しなかった。