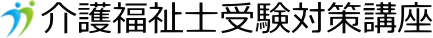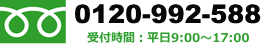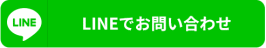出雲市の皆様、介護福祉士講座の5つの特長です
出雲はこんな町です
出雲市(いずもし)は、島根県の中東部に位置する市。県内で2番目、山陰地方では4番目の人口を抱える。現在の出雲市は、2005年3月22日に旧出雲市・平田市・簸川郡大社町・湖陵町・多伎町・佐田町の2市4町が合併してできた自治体である。旧出雲市は、室町時代以来、物資の集散地となった今市を中心として、周辺の村が合併して成立した市である。 出雲平野を中心として、北は日本海、南は中国山地に接する。市の東側には斐川町との境界を成す斐伊川が流れ、宍道湖に注いでいる。 肥沃な出雲平野を背景として古代から発展し、特に弥生時代以降は、西谷墳墓群など大型の四隅突出型墳丘墓が造る大きな勢力が存在した。6世紀後半には今市大念寺古墳や上塩冶築山古墳など、県内でも最大規模の古墳が造られた。また記紀神話においては出雲が舞台とされ、出雲大社の創建が語られるなど、朝廷から重視された地域でもあった。 鎌倉時代には、出雲国守護・塩冶氏が本拠地としたが、塩冶氏としての最後の守護塩冶高貞(塩冶判官)は室町幕府執事高師直によって滅ぼされた。 江戸時代には、大部分が松江藩領だが、大社町の一部は幕府より認められた出雲大社領や日御碕神社領とされ、また佐田町の一部は平安時代から続く京都・石清水八幡宮領とされている。 近世後期以降、出雲平野は「雲州木綿」の集散地となり、特に旧平田市にあたる楯縫郡では、明治初期の記録において木綿の生産高が米の生産高を上回るほどであった。また大正時代から昭和30年代にかけては、出雲製織(のち大和紡績)、郡是製糸、鐘淵紡績などの工場がつくられ、繊維工業の町となった。 前西尾市長の前に岩國哲人氏が市長であり独創的な市政を行ったことは有名。